プログラムの原稿プレビュー
-

チェ・ウォンシク(韓)
CHOI Won-shik東アジア文学共同の家
チェ・ウォンシク (CHOI Won-shik)
1、家作り
今回の基調報告は私の告別の辞です。10年前に開かれた最初のフォーラムから、2巡目が始まった今日に至るまで 、東アジア文学フォーラムの経過を振り返ると、迂余曲折さえも輝いて見えます。いや、そのすべての迂余曲折こそが、フォーラムの肉体であり魂であると言っても過言ではないでしょう。私たちがともに建設した東アジア文学フォーラムという家は、ある有名な建築家が机上で一人でさっと作った蜃気楼ではなく、この家に入居する3か国の作家が思案の末に積み重ね、暮らしながら作り直し、またおそらく新規入居者が入るたびに修正が加えられ、完成がたえず延期される、言い換えれば、完成がすなわち未完となる「共同の家」(the common house)だからです。H・D・ソローの言う「このような無意識的な生活の美しさ」(a like unconscious beauty of life)とは、まさに私たちの東アジア文学フォーラムにぴったりの言葉でないかと思います 。
国、国民、言語の境界を越えることがどういうことかを実感した10年でした。よく考えてみれば、「越える」という言葉に語弊がなくはありません。二者の関係ならば越えるという言葉がもっともですが、三者となれば越えることはできません。三者はすでに世界だからです。「かける」という意味をもつ中国語の「跨」(kua)が、私たちのフォーラムを示すのに最も近いでしょう。フォーラムに入った瞬間、私たちは「異なる世界」の市民として、中国語、日本語、韓国語の間に鎮座することになりますが、さらにこの3つの言語は、中国の『詩経』、日本の『万葉集』、韓国の『三代目』 以後、なんと千年余りの間、切磋琢磨されてきた高度な文学語です。そのおかげでこのフォーラムに参加した作家たちは、突然、未知の時間や未知の空間から到着した、果てしない諸言語の間をつなぐ連絡員としての責務を抱え込むことになりますが、未知の読者たちの呼応で、その責任はほのかな喜びへと突然変身したのです。この「共同の家」を暖かく包んだ韓・中・日の3か国の読書共同体の、低くはあるが堅固な擁護こそ、まさにフォーラムの今日を導いた決定的な山であったことを、誇らしく告白したいと思います。
(後略) -

ティエ・ニン (中)
TIE NING時間とわたしたち
ティエ・ニン (TIE NING)
十年前のこの豊かな季節に、第1回東アジア三か国文学フォーラムがソウルで開かれました。そして十年後の今日、第4回韓中日アジア文学フォーラムがまたソウルにやってきました。十年前の当時、フォーラムに参加した三か国の作家たちは互いにまだ見知らぬ仲でした。けれど、あの日から十年が過ぎた今日という日に再会して、わたしたちは親しみのある目線で互いにこう伝え合うのです。“時間よありがとう。わたしたちがめぐり合ってからこんなに長い間お互いを友としてくれて”。
ここまで書いてきて「十年树木(十年、木を樹つ)」という中国の古い言葉を思い出しました。これは中国の春秋時代の有名な政治家管仲の言葉です。これは「ひとつの苗が大樹へと成長していくのには十年の歳月が必要で、まして森にまでなるのはそう簡単ではない」という意味をもちます。この言葉の「树」は育成と栽培を意味する動詞です。アジア文学フォーラムは十年の年月を経て、参加者全員の協力のもとに、小さかった苗木はすこやかな大樹へと成長しました。しかもそれだけではなく、参加者にとってのひとつの森林へとなっていくのです。もし、フォーラムの各作家自身をそれぞれ独立した文学の木と譬えるとすれば、まさに皆さんの集まりこそこのフォーラムを文学の森にしているのです。(後略)
-

平野啓一郎(日)
HIRANO Keiichiro (PHOTO©MIKIYA TAKIMOTO)作者と作品、読者と現実の狭間に立って
平野啓一郎 (HIRANO Keiichiro (PHOTO©MIKIYA TAKIMOTO))
第四回目を迎える東アジア文学フォーラムに、日本の一作家として、また日本の作家団の団長として参加できますことを、大変光栄に存じます。
まず始めに、今大会の開催に向けてご尽力くださった韓国、中国両国の関係者の皆様に、心よりのお礼を申し上げます。
2008年の第1回ソウル大会、2010年の第2回北九州大会、そして2015年の第3回北京大会と、1巡目のフォーラムは大成功裏に終えましたが、日本は実は、2巡目以降のフォーラムへの参加が極めて難しい状況にありました。
勿論、このフォーラムの重要性を確信しているという点では、日本の実行委員会も中国、韓国と完全に価値観を共有していましたが、問題は主に財政的な事情でした。
しかし、2巡目のフォーラムの開催を模索する過程で、韓中両国は、常に情熱に満ちた温かい励ましで私たちを勇気づけ、最終的には韓中共催というかたちながら、日本にも従来通りの参加枠を設け、十人の作家をここソウルに招待してくれました。
両国の実行委員会が、このフォーラムにとって、日本の作家の継続的な参加は欠かせないと、最大限の敬意を以て、熱心に説得してくださったことに、どれほどの感動を覚えたかは、言葉に尽くせません。第4回目のフォーラムのテーマは、「21世紀の東アジア文学、心の連帯」ですが、このフォーラムの存在自体が、まさしくその「心の連帯」を体現していることを、最初にまず、深い感謝を込めて、強調しておきたいと思います。
10年に亘るこのフォーラムに、私は最初からすべて参加する幸福に恵まれ、思い出話をし出せばきりがありませんが、一つだけ、強く印象に残っているエピソードを紹介したいと思います。
第1回ソウル大会のあと、私たちは春川に移動し、そこでも幾つかの文学イヴェントを催しました。その一つとして、現地にゆかりの作家、金裕貞を記念する「金裕貞文学の夜」という屋外のフェスティヴァルに参加しました。10月3日のことです。
ステージ上で歌や踊りが披露され、広大な公園内ではバーベキューも振る舞われて、とても楽しい一日でしたが、ただ一つの問題点は、尋常でなく寒かったことで、作品の朗読をする予定だった私は、ステージ上でずっと震えていて、聴きに来てくれた他の作家や現地の人たちもやはり、凍えている様子でした。
私の隣には、莫言氏が座っていました。それぞれの作品を順番に朗読してゆく企画だったので、私たちは、その間、一言も会話をしませんでしたが、終わって私が思わず英語で、「寒いですね。」と話しかけると、彼は本当にそうだという風に笑いながら、私の二の腕のあたりをゴシゴシと何度も撫でさすってくれました。
莫言氏の作品は、以前から『紅い高粱』や『酒国』を読んでいて、その時は丁度、日本語訳が刊行された『転生夢現』の、「義牛」として死んだ主人公が、閻魔大王にロバに転生させられたことの不平を訴えている箇所にさしかかったところでした。
莫言氏は日本でも非常に評価が高く、その存在は些か神秘化されていて、私はこんな爆発的な想像力の物語を書く小説家は、一体、どんな人なのだろうかと、畏敬の念を抱いていましたので、その人に腕をさすってもらったことに、強い印象を受けました。(後略)
-

クォン・ヨソン(韓)
KWON Yeo sun韓国の小説家Kの履歴書
クォン・ヨソン (KWON Yeo sun)
私は1965年に韓国の南方の街・安東(アンドン)で生まれ、これまで韓国の外に出たことがありません。私は韓国語以外の言語ができず、韓国語でない言語で書くことを考えたことがありません。私の小説がどう翻訳されるのかを念頭に置いて作品を書いたこともありません。私はひたすら韓国語の限界の中だけで作品を書き、韓国語で表現される言語的形象だけを知っています。
翻訳された作品で、魯迅や村上春樹をはじめとして、中国や日本の代表的な文人や作家らの作品を読みましたが、中国や日本の文学に造詣が深いとは言えません。そのような私が韓・中・日フォーラムに出て基調報告をするということは、他の見方をすれば無謀で不条理なことのように思います。ですが観点を変えて考えれば、何かをすでに知っているという考えの危険性が、それを知らないということを知る危険性よりも、より大きいかもしれません。ですから私は、自分の無知を認めた上で、自分ができることだけをすることにしました。それは韓国の小説家として、自分が体験した韓国文学の場について、簡単にご報告さしあげることです。
私は1996年に文壇にデビューしました。韓国では新聞や雑誌などを通じて作品が当選する「文壇デビュー(登壇)」制度が、作家として必須の入門過程であると考えられています。デビュー後、ずっと続けて作品を書いてきたわけではありませんが、名目上、私はデビューして22年たっている小説家で、私がその時間の間、通過してきた韓国文学の軌跡は、韓国文学にいくら造詣が深い中国や日本の文人にもわからない、特殊で矛盾の多い局面を含む可能性もあります。作家としての私の歩みが、韓国の作家の中で代表的だったり典型的であるとは言えませんが、すべての作家の歩みがそうであるように、私の個人的で主観的な歩みもまた、韓国文学の内密な普遍性を示すアレゴリーであるとも思います。
私がデビューした1990年代は、韓国現代文学で妙な接合と断絶が起こった時期です。世界史的に社会主義圏の没落が始まった時点で、このとき韓国では、80年代の民衆文学が退いたところに、一方では80年代に対する「後日談」の文学が、他方では個人の内面に注目する新しいスタイルの文学が出てきました。私の最初の小説は、2つの傾向の間で実に不明瞭なポーズを取っていました。表面では「後日談」小説の形式を取りながら、中では奇怪な内面を描いていました。この最初の小説の中に、その後の私の文学的苦闘と彷徨が、さらに果敢に一般化して言うならば、私の属した「386世代」の苦闘と彷徨が、萌芽形態として存在していたとも言えます。
「386」は韓国で最も有名な数字の組み合わせの1つです。この組み合わせは1990年代に初めて登場しましたが、本来はコンピュータシステムを称する言葉から、1つの世代、韓国現代史で消し去ることのできない一世代を称する言葉として転用されました。いわゆる「386世代」とは、1990年代に「30代」であり、「(19)80年代」の入学年度であり、「(19)60年代」に誕生した世代のことをいいます。彼らはこれまで、韓国社会のすべての領域で多大な影響力を行使してきましたが、その評価は極端に分かれたりもします。おもしろいのは、386が「現在-20代-誕生」の順序、すなわち時間の逆の順で並んでいるという点です。偶然の命名でしたが、この世代にとって運命の烙印となったこの組み合わせは、最初のケタの数字が時間の流れで「486」「586」と変わっていきますが、後に続く2つの数字は固定されています。それは彼らのアイデンティティが、最初のケタの数字の変化と関係なく、その後につづく不動の地層、つまり「変革の時代」といわれる80年代と、朝鮮戦争以降のベビーブームが起こった60年代という過去の地層に、固く釘付けされていることを暗示したりもしています。(後略)
-

チュ・ファドゥン (中)
QIU HUA DONG東アジア文学地理学構築の新たな景観
チュ・ファドゥン (QIU HUA DONG)
地理的にいえば、ウラル山脈からコーカサス山脈に至る一筋の線を東境に、そして西にはポルトガルのロカ岬からヨーロッパの最北地点であるノルクィン岬から、そして最南端地点のタリファ岬にわたるまで、これが偉大な欧州大陸である。ここ二、三十年の間に、ヨーロッパは全方位的な一体化メカニズムを構築するため、総力を挙げてより強大な欧州連合(EU)を作りあげた。浅はかとはいえ世界主義の思想を標榜しているにもかかわらず、自ら流動的で、国家に縛られないヨーロッパ人だと考える人はまれだ。地理的に地球はほぼ円形に近く、西半球と東半球に区別できる。しかし、現代的な意味で、地球全体のイメージはほぼ“西欧とそれ以外”(the West and the Rest)"(スチュアート・ホール)に大別される。“欧州とアジア”はこのような二元対立構造の変形である。今私たちがここに集まった理由は、アジアとわれわれの共同体である東アジアを談論するためである。
アジアは広大な面積に多くの国が分散しているが、東アジアの国々は隣接していて、中国と日本、そして韓国が昔から一衣帯水(帯のように狭い川を挟むほどの近さを比喩する)の隣人関係にある。地理的にいって東アジアは三国のほかに朝鮮とモンゴルを含んでおり、ある人はベトナムが儒学文化圏にあったという点から広義の文化的東アジアとみなしている。しかし、中国、日本、韓国の三国には、「現代化」というそれなりの理由がある。“ASEAN+3”(1998年にASEAN10ヵ国[マレーシア、タイ、シンガポール、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー]と韓国、日本、中国が設立した国際会議)の構造は、中国と日本、韓国を整合可能な現代化地域共同体とみなしているという論理を傍証する。したがって、東アジア文学の地理学はまさにここにその輪郭をみることができる。(後略)
-

中島京子(日)
NAKAJIMA Kyoko21世紀の東アジア文学・心の連帯 ――風の吹き渡る場所
中島京子 (NAKAJIMA Kyoko)
私に与えられた主題は、「21世紀の東アジア文学・心の連帯」というものです。
深く考えずに講演をお引き受けし、後でその重大さに気づいて困惑しました。あまりに大きな主題なので、私のような三文文士には扱い兼ねるものだと思われたからです。ところで三文文士という言葉は、中国語や韓国語には、あるのでしょうか。原稿料の安い、たいして価値のない小説を書いている作家という意味です。江戸時代の三文は、いまのお金で100円くらいかもしれません。さすがに私も、100円で仕事をしようとは思いませんが。
難しいこと、大きすぎることは苦手なので、小さくて易しいことから始めようと思います。何年か前に、ある雑誌に私は、自分がお隣の国・韓国とどのようにして出会って来たかを書いたことがありました。これを下敷きに、文学を中心にして、そして、中国ともどのように出会って来たかを加えて、その延長線上に見えてくるものについても少し考えてみる。このようにして、私に与えられた難題を乗り切ろうと思います。今回はフォーラムのホスト国が韓国ですので、韓国編から始めます。
〇韓国文学との出会い
私が最初に出会った韓国文学は、『ユンボギの日記』でした。70年代の初め頃だと思います。日本語に翻訳され一般読者に向けて出版された最初の朝鮮文学だそうです。貧しい男の子が弟や妹の面倒を見ながらたくましく生きる物語でしたが、同じころに読んだ日本の第二次大戦後の貧しい少年の話と印象がいっしょになってしまい、外国だということがうまく思い描けませんでした。そのころ、韓国はいまよりずっと遠いところでした。
『ユンボギの日記』を読んでいたころは小学生で、東京近郊の団地で、両親と姉の四人で暮らしていました。そのころ家に金芝河の詩集があったのを覚えています。父はフランス文学を専攻する学者で、書斎から出たがらない人でしたが、金芝河が好きでした。父は、詩集を読む以外のことはあまりしませんでしたが、当時の大学人や言論人はみな、多かれ少なかれ、韓国の状況に関心を寄せていたのです。(後略)
-

キム・エラン(韓)
KIM Ae-ran光と借金
キム・エラン (KIM Ae-ran)
「伝統」という言葉を聞くと、死んだ人のことがまず思い浮かぶ。彼らが私に与えたものと与えていないもの、与えたのかもよく知らずに渡したものなどが思い浮かぶ。同時に、私がもらったものともらおうとしなかったもの、もらったのも知らずにもらったものも。
古いものはは大部分小さくなり、小さくなって闇の中に消えるが、唯一、昔話を思い出すと、どうして光を連想するのかわからない。長い話の中、ある光が突然、物語の温度を変える時、誰かの顔を未知のものとして照らす時、私の身体に起こった緊張が、感光フィルムのように残ったせいかもしれない。あるいは、物語が生まれた場所に、光が、火のある場所に、口と耳がいつもあったせいなのかも。
私は相変らず経験と知恵が足りないが、本を通じていろいろな光と出会った。その中には、暗い深海を探る探照灯があり、信念に燃えたたいまつもある。誰かが飯を炊く火や、銃口の中の火炎、受難者の星の光をはじめ、人々がよく「火の玉」「魂火」と呼ぶ、青白く不可解な物質もある。
そのなかで、ある火は、今でも私に、原初的な恐れを呼び覚ます。李清俊(イ・チョンジュン)の中篇「うわさの壁」に出てくる「懐中電灯のあかり」がそれである。〔朝鮮戦争のさなかの〕真夜中、突然ドアを開けて入ってきて〔北か、南か〕「おまえはどっちの味方か」と問うあかり。こちらの答え方によって死ぬことも生きることもあるが、まったくあちらの実体が見えずに凍りついた、ある家族のことが思い浮かぶ。だから私には、あのまぶしい追及、あるいは暴力が、韓国現代史の重要な場面のように思われるが、それは、これまで続く韓国の多くの葛藤の裏面に、あの懐中電灯のあかりが目の前にちらつくからである。(後略)
-

チョン・ソンテ(韓)
JEON Sung-tae死語事典
チョン・ソンテ (JEON Sung-tae)
夜便をしながら、うずくまって座っていると、向かいの家の柿の木の上にあるカササギの巣が怖く、自分の影が動くのも怖かった。とても寒い夜だった。おばあちゃん、おばあちゃんと呼び続け、おばあちゃんが、わかった、わかったと応え続ける。おばあちゃんが他所の方を見てるんじゃないかと心配だった。
子供が夜便をするのは、大晦日の夜、ニワトリにお辞儀をすれば治る、ニワトリにお辞儀をしなさいと言われた。そんなにつらいことでもなく、恥ずかしくて我慢できないことでもなかった。小屋のなかのニワトリも、お辞儀をされて、クルルッ、クルルッと鳴いていた。
流星をもし食べられたら、長く生きられるということだった。流星を拾ってきたという人がいた。あの日の晩も流星がさあっと矢のように落ちた。おじさんが一度、ウズラを生きたままつかまえてきた、あの裏山の松林の中に、本当に落ちたのだ。
流星が落ちたところを
心に留めて
次の日に行ってみようと
ずっと思い続け
いつの間にか大人になった
――鄭芝溶「流星が落ちたところ」(散文)全文
韓国語の語法にかなった散文である。私はこれを韓国の散文の白眉と考えて親しんできた。1つの散文の中で、主語が「ぼく」「おばあちゃん」、または「自然物」と、互いにつつみつつまれて、3つ、4つの呼吸の長い文章として流れていく。すると突然しぼられて、1つの呼吸で結ばれるが、その文章が石英の石のようにつめたい。なのにまた悠長である。話は3度転換するが、子供の話し方のようによどみなくすっきりしている。ニワトリに年末の挨拶をする民間の風俗で、夜便の話が流星の話にいきなり変わる。話の広がりがかなり遠く、また果てしない。風景があり、自然と神話に照応する精神があり、微笑ましく広く果てしない抒情がある。韓国語の話し言葉の活力はもちろんのこと、伝承世界の味をきちんと生かした、散文のなかでも一番である。
だが、今となっては絶滅し、出会うこともできない文章である。近代100年の疾走の中で、韓国語の使用者は新人類と同様に変わり、語文構造はもちろん、自然に対する無垢の好奇心と親縁性を失った。(後略) -

スー・トン (中)
SU TONG伝統:民間の想像力の活用
スー・トン (SU TONG)
伝統という議題について論じようとすると、故人と先輩について論ずることもできるし、単に自分自身について論ずることできるだろう。ある人がどんな書き方を守り抜こうが、彼が伝統を尊重する人であろうが、あるいは伝統に逆らう人であろうが、その一生を総括してみると、伝統というこの巨大な建築物を取り囲んで、忙しく叩きながら修補する伝統の左官に過ぎないと、私は思う。
伝統は人々に滋養分を提供するが、この滋養分を提供する方式と経路は限りなく多様である。人々が自分の民族文学の伝統に対して感謝の念を表現する時、言外の意味は屡々李白と杜甫、蘇東坡と李淸照、『紅樓夢』と『金甁梅』に感謝するという意味となる。これはすべて経典的作品に対して感謝するのであり、伝統という建築物の最も華やかで精巧な部分に対して感謝するのである。私たちがこの建築物の基礎について探索することはごくまれである。基礎がどうだというのか。基礎は当然建築物に隠されていて、実際に注目を受けることはなかっただけではなく、その場にずっとそのまま存在していた。基礎はどんな材料で構成されているのだろうか。勿論あまり多いので一々数えるのも難しいだろう。普通別途のものとして分類される神話、伝説、民話、文字記録の残っていない童謡、山村の歌謡、民謡などが基礎材料に含まれるだろう。そこには世界に対する人類の最も原始的な文学的想像力が篭っている。それらは民間に由来しながらどのようにして私たちの滋養分になってきたのであろうか。実際、私たちはとてもよく忘れる習性を持っている。言い換えると、一人の作家の世界に対する想像力が最も優れていて、よく訓練された文字として現れて成果を出す時、人々が偉大な作品が誕生したと声高く歓呼する時はおそらく丁度山村の歌が無くなる時期であろう。偉大な作家がどんどん増えていく時代に、民間に根付いた想像力の花々は山野の中で黙って萎んでいくのである。(後略) -
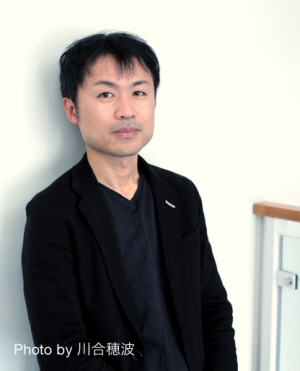
阿部公彦(日)
ABE Masahiko (PHOTO©KAWAI HONAMI)日本語と声の文化
阿部公彦 (ABE Masahiko (PHOTO©KAWAI HONAMI) )
この一年ほど、私は大学入試政策に対して反対意見を表明してきた。ツイッターで頻繁にコメントを流し、『史上最悪の英語政策――ウソだらけの「4技能看板」』なる本を出し、メディアでインタビューを受けたり寄稿したりする機会も多かった。そのせいか、以前からお付き合いのある方々からは「いったいどうしちゃったの? ふだんの仕事はどうしたの?」と訊かれたりもする。
しかし、この入試騒動は、文学や文化全般の問題にも直結すると私は考えている。
政策の土台にあるのは、簡略化していえば次のような考えである。大学教育の最大の目的は、会社で「使える」人間を育てることにある。とくに今の日本の会社員に足りないのは、「使える英語」を操る能力。使える英語とは何よりも「しゃべれる英語」である。「しゃべれる英語」を身につけるには、民間試験を導入するのが一番……ざっとこんなところである。つまり、キーワードはスピーキング。もっと馴染みのある用語でいえば、「英語の文章なんか読めなくていいから、もっと英会話をやろう」ということだ。
こうした英語政策に、「うん、そうかもね」とうなずく人は相当数いるだろう。その背後にあるのは、会話と文章とは異なるものだ、とする考え方である。だから、語学学習でも「読解」か「会話(発話)」か、という二分法になる。今回、「4技能」という看板がしきりに立てられているが、「4技能」というのは見せかけだけで、実質的に争点になっているのは「読み」か「しゃべり」かというポイントなのである。
なぜ、こうなるのだろう。実は、先頃ある国際シンポジウムに参加する機会があったので、英語を母国語とする人に日本の入試政策の現況について説明してみたのだが、みなさん、なぜ日本人が「文章」(written English)と「会話」(spoken English)という二分法にこだわるのかわらかないと言う。ひょっとしたらそれは「知性主義」と「反知性主義」の対立なのか?という意見さえあった。
実はこの問題はけっこう根深い。私が思い出すのは、明治から大正にかけての「言文一致運動」である。日本では当時、いわゆる文語(書き言葉)と口語(話し言葉)の間の乖離が大きかったため、西洋風の小説を導入しようとした文学者を中心に、このギャップを埋めようとさまざまな試みがなされた。その試みは文学という領域をこえ、他のジャンルにも波及し、やがて日本語の書き言葉の性質や、ひいては言論の形式にまで大きな変革が起きた。(後略)
-

若松英輔(日)
WAKAMATSU Eisuke伝統はどこにあるのか
若松英輔 (WAKAMATSU Eisuke)
世界が同時多発的に右傾化し、「伝統」回帰を口にし始めている。日本も例外ではない。貧しき伝統主義の弊害は、教育現場や憲法改正といった、私たちの日常生活を脅かすところまで来ている。
だが、伝統を重んじるという人々からは、「伝統」とは何かを考え得る根源的思索の成果をうかがい知ることはできない。伝統とは何かを考えないまま、伝統的であるべきであると主張する人々が跋扈している。
伝統を重んじることが、単に時間的過去にさかのぼることを意味するのなら、私たちは最後には、文化と呼ぶに値するものを産む以前の「原始的」と呼ばれる状態に戻らなくてはならなくなる。たとえ、これが極端な言説であることは理解しつつも、伝統を単に時間的現象であるとするなら、どの地点まで遡及すればよいのかという問題は最後まで残る。
伝統主義traditionalismは、思想、文化、宗教的活動のある、あらゆるところに生まれ得る。伝統主義はいたずらな進歩主義の敗北を機に目覚める。それは簡単に原理主義fundamentalismに結びつく。また、伝統主義がファシズムと融合するとき、制御できない狂信的うねりになることを私たちは知っている。「伝統」は、そのよみがえらせ方を誤れば、人間ばかりか、ある文化の一時代を飲み込むほどの威力を有しているのである。(後略)
-

チャン・カンミョン(韓)
CHANG Kang-myoung差異を可能にするものなど
チャン・カンミョン (CHANG Kang-myoung)
以前、どこかで読んだ話ですが、小説家は小説を書いた後にすぐに死んでしまうのが、読者のために最もいいのだそうです。読者の立場では小説家の説明ほど、読書をダメにするものはないというのです。
私はこの言葉に一理あると思いますが、だからといってすぐに死にたくはありません。少しぎこちないですが、読者の読書の邪魔をしないことを願いながら、私の短篇小説「蚊」、そして今日の主題である「差異」について話してみます。なんとなく「あの人はあのように考えるんだな、私は自分の考える通りに読まなければ」という心持ちとして、受け入れて下さればと思います。
短篇小説「蚊」は、私が2012年に出した連作小説集『リュミエールピープル』に収録されています。ソウル市西大門区新村洞にある仮想の小規模オフィスビル「リュミエールビル」の8階に住む人々の話で、短篇10編がゆるくつながっています。「蚊」はこの小説集の2つ目の短篇で、なので802号で起きる出来事として設定しました。
この小説集に収録された短篇は、すべてうす暗く幻想的な雰囲気です。短篇「蚊」もそうです。すべて読んでも、身体が麻痺した中年男が女の子の状況を想像するものなのか、女の子と呼ばれる若い女性が、身体が麻痺した中年男を想像するものなのか、よくわからないように書きました。そして、隣りに住む聴覚障害者の話と憂鬱な妊産婦の話が1回ずつ言及されます。
この小説を書いた時、私は37歳でした。この当時、私は韓国社会の堅固なシステムについて多くの関心を持っていました。韓国は1960年代から2000年頃まで、かなりの速度で産業化と民主化を成し遂げました。激烈な変化の時期であり、当時の若者たちにはそれだけ機会が多かったのです。そうだったのですが、2000年以降は明確に社会の躍動性が減少しました。
一方では、この場にいらっしゃる方々がみな経験されたように、2000年以降、どこの国でもグローバリゼーションが急速に進みました。このグローバリゼーションはいろいろな層で同時に展開された単一化でした。言ってみれば、政治と経済はそれぞれ民主主義と修正資本主義に、生産と消費は企業的合理性と効率性を追求する「マクドナルド方式」に、文化は「若さ、豊かさ、セックス」を重視するアメリカ大衆文化に似通っていく方向で発展しました。そうするうちに、少なくとも先進国の間では人々の生の様式がますます似ていく現象が見られました。人々がますます似たような服を着て、似たような食べ物を食べ、似たような音楽を聞き、似たような考えをするようになったのです。(後略)
-
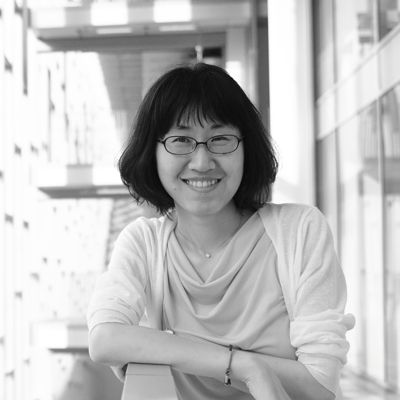
チン・ウニョン(韓)
JIN Eun-young東アジア、差異と心の連帯
チン・ウニョン (JIN Eun-young)
韓・中・日の3か国の作家が互いに出会い語る「差異」はどのようなイメージか考えてみる。それはアンリ・マティスの作品でたびたび見かける、青と黄色、あるいは赤と黄緑のように、強烈な対応を作り出す差異のようなものだろうか? あるいは春に美しく咲く、梅や桜、あんず、この3種の花が示す差異のようなものだろうか? これらの花は、知らない人たちが見れば区別しにくいほどに似ているが、よく知る人たちには、この花を混同するということ自体が奇妙に感じられるほど、互いに違って見えたりもする。私たち東アジアの人間は、類似と差異を同時に示す3種の花や木のように、似ていながらも異なっているようである。
白く小さな春の花を見下ろせる研究室の書架から、リルケの詩集を取り出して読んでいてら、美しいイメージを1つ発見した。リルケは、同じような外見の部屋の間で、互いに異なる時間が過ぎるのを見る。これがリルケの考える差異のイメージである。
見よ、彼女たちが同じ可能性をどれほど
異なる方式で受け入れ、広げていくかを、
それはあたかも、私たちが2つの同じような外見の部屋の間で
それぞれ異なる2つの時間が過ぎるのを見るようだ。
――R・M・リルケ「姉妹」より
私たちは長い間、東アジアという同じような外見の部屋に居住してきた。しかし私たちは、同じ可能性を全く異なる方式で受け入れ繰り広げ、近代化の過程でこの点が如実にあらわれた。私たちは似たような環境で育ったが、全く異なる気質を持った姉妹のように違う。ならば、私たちは強い個性を持ちながらも、互いに対してそのいちいちがわかる姉妹のように、深い友愛で過ごすのだろうか? 私はもちろんそうなればと希望する。だが、「姉妹」のその後の連で、リルケは彼女たちの運命に対して違うことを考える。詩人は暖かな希望について語る代わりに、現実を冷静に伝える。(後略)
-

チャン・ウェイ (中)
ZHANG WEI森と海と犬 -『父の海』創作背景-
チャン・ウェイ (ZHANG WEI)
過去を思い起こすとき、心の中に三つのものが浮かぶ。森、海、犬。これらは私の幼年時代と切り離せない。海辺の平野に森があり、犬やその他多様な動物たちが生息していて、私もやはり、かれらの間を行き来しながら過ごした。
学校に通い始めると、幼年の私はいくぶん縛りを受けることになった。しかし校門さえ出れば、私たちはいっせいに浜辺に向かって駆け出した。海辺の森は深かったが、人通りはほとんどなく、小さな村がいくつかばらばらにあるだけであった。猟師、薬草師、漁師たちがこの森で活動していた。森にまつわる伝説は多かったが、その内容のほとんどは遥か昔に造られたもので、主に人間が動植物を害さぬよう悟らせるためのものだった。これらの伝説は、人間と動植物が平等だという理念に基づいていた。要するに言い伝えは、人がしばしば動物の善良さや知恵に及ばないこと、古い木のほうが人より価値がある、といったことを教えていた。
国営林業農場の労働者たちは私たちにとって非常に重要な存在であり、われわれもまた、彼らにとって同じくらい重要であった。私たちは彼らの話を聞き、彼らがくれたおやつを食べ、彼らの犬を見物した。果樹園の人たちはまた少し違って、関係が良好な時はとても親切だった。 冬と春はいつも関係が良い季節だった。その季節に彼らは畦を補修し、水を与えて枝を切り、茂った花畑で仕事をした。彼らは優しかった。冗談を言い合いながら互いに食べ物を配ったり、行き来が頻繁な主人同士も、互いに笑顔で迎えた。しかし、いったん果物がぶら下がり始めると、事情は変わった。その時期から彼らの気性は荒くなった。理由は、私たちが頭を働かせて果物を頂戴したからだった。今振り返ってみると、幼い頃のサクランボ、スモモ、りんごへの欲求は本当に不思議なものだ。とにかく盗りたかった。果物を食べたいという欲求がすべてだった。その時期を、私の生涯における「果物時代」と命名できるほどだ。(後略)
-

チャオ・ユウィン (中)
CAO YOU YUN心の連帯-父親世代における卓越した東アジアの詩作
チャオ・ユウィン (CAO YOU YUN)
この文の中で、私は三人の東アジアの詩人について話そうとしている。なぜなら、彼らが半世紀を越える長い期間、詩作を通じて東アジアの詩歌に関する過去と現在、未来を明瞭に開示することによって私たちに深い感動を与え、また暖かい激励をしてくれているからである。彼らは私の父親と同じく1930年代に生まれたので、私は彼らを「父親世代」と呼ぶことにする。その三人は日本の詩人である谷川俊太郎(1931-)、韓国の詩人である高銀(1933-)、そして中国の詩人である昌耀(1936-2000)である。当然、この三人の先輩たちはみんなそれぞれの国で卓越な詩人であり、また偉大な詩人である。三人の中で、高銀さんと谷川さんは依然として健在であり、昌耀さんは2000年3月、ミレニアムの曙光がこの孤独な行星を照らしていた春のある日、急にこの世に別れを告げた。私は一般読者の立場から中国の伝統に従って(私たち東アジアの伝統でもある)一番年長者である谷川さんの話から始めたいと思う。
私が谷川さんをはじめて知ったのは、比較的に早い時期で、1990年代に彼の詩集を手にいれ時である。ゴルムド市のある文具店の図書コーナーで買ったのだが、その詩集の所在は何回か引越しを重ねるなかで本の山の中に埋もれて、今は不明になってしまっている。幸いに、その後谷川さんの代表作、つまり彼の知己である訳者田原さんが谷川さんと一緒に精選し翻訳した新しい詩集『二十億光年の孤独』をまた買うことができた。(後略) -

島田雅彦(日)
SHIMADA Masahikoこのまま黄昏れちゃっていいのか、人類
島田雅彦 (SHIMADA Masahiko)
冷戦時代の世界終焉イメージは核戦争による破局とその後の世界を想像することで磨き上げられた。放射能汚染された廃墟で、どのようにサバイバルするのか、通俗的に定着したのは、「マッドマックス」やその焼き直しでもある「北斗の拳」に見られる弱肉強食の無法地帯のイメージだった。
現在は核戦争に加え、化石燃料の過剰消費による地球温暖化やパンデミック、未曾有の大地震や大津波、原発事故など「大破局」をもたらす要因は増えたともいえる。私たちは人命救助や避難生活、都市インフラの復興には想像力が及ぶ。誰しも戦時下の窮乏生活や経済封鎖下で、あるいは震災や大停電を通じて、百年、二百年前の生活に逆戻りした経験があるからだ。人類はそのような「小破局」には馴れている。だが、「大破局」は文字通り人類と文明の滅亡であるから、その先のことを考えても意味がないと思い倣わしてきた。
それでも「大破局」後を生き残る者もいるだろう。彼らは罪悪感や義務感から、あるいはいつまでも石器時代にとどまっていたくないという思いから、失われた文明の保存あるいは復活を目指すかもしれない。それは高度な分業を自明としてきた現代人には大いなる試練となる。産業革命のプロセスを律儀に辿り直すことに近い。始めのうちはコンビニやスーパーに残った食料、生活必需品を漁る都市部での狩猟採集生活で何とかなるが、その後は水、食料、燃料、情報などの調達に苦労することになる。川の水の濾過や燃料になる薪探しを始めることになる。やがて、農業を始めなければならず、それに伴い、様々な道具、部品、機械を自分で作り、労働効率を上げたくなる。その場合は燃料や電力も手に入れたくなるし、ほかの生き残りとの接触を図るために移動や輸送、通信の手段を確保する必要が生じるし、病気になれば、薬がいる。電力復旧にこだわるなら川の流れを利用した小規模水力発電かソーラー発電が現実的だろう。近頃の狩猟や農業、家内制手工業への回帰傾向は、単なる懐古趣味にとどまらず、消費文明の黄昏の後に巡ってくる危機の時代に対処するための準備となる。むろん、文明の再建はゼロからは始められない。過去の技術や叡智を蓄積する図書館や博物館は再建の出発点になる。(後略)
-
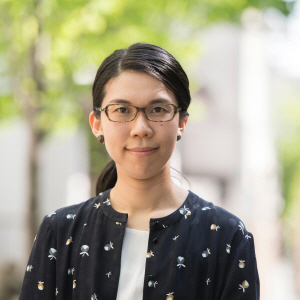
小山田浩子(日)
OYAMADA Hiroko (PHOTO©SHINCHOSHA)差異の交わり
小山田浩子 (OYAMADA Hiroko (PHOTO©SHINCHOSHA))
私の小説は幻想、とか、奇想とか、そういう言葉で評されることがしばしばある。たとえば作中に図鑑に載っていない動植物がでてくるとき、あるいは、ごく身近な生き物が不思議な行動をとるとき、そしてそのことに対する人々の反応が一様でないとき。書かれた小説はどのように読まれても書き手としてはありがたい。ただ、書いている方の実感としては、すべては、どんなありえないようなことでも、変なことでも、現実と幻想に差はないという風に思っている。それは、現実の寓話としての幻想的な要素という意味ではなく、どれもが本当にあったことなのだ。もちろん小説で書かれているすべてが現実そのままというわけではない。でも、読者の方が多くこれは想像だろう、幻想だろうというところの根っこには、形を変えた、もしくはそのままの、私自身の経験や体験がある。
今回提出した「叔母を訪ねる」という掌編は、夢で見た情景を元に書いている。夢は私の脳内でしか起こっていないがでもまぎれもない現実だ。私は実際にそれを見て、嗅いで、感じて困惑した。夢から覚めて、これを書こうと思ってすぐ書いた。ほかにも、そのようにして夢を元に書いた作品がある。また、小説に出てくる動植物もよく夢で見たものを書く。夢の中の生き物たちは、何かと何かが混ざり合っていたり、何かが欠損していたり凝視しようとすると形を変えたり消えてしまったりするが、その質感や湿度を私は確かに感じたのだ。そして、そういう夢の中の出来事や生き物たちの不思議さと、たとえば近所にある田んぼで泳いでいる小さなエビやヒルや、あるいはテレビや図鑑が教えてくれる遠い外国の派手な色をした蝶や瓢箪のような鼻をぶら下げた猿らの不思議さには何ら差がない。違いはそれを実際に見たかどうか、感じたかどうか、体験したかどうかということだ。私はテレビで見た不思議な猿と一緒に過ごした話を書くことはおそらくできない(テレビで不思議な猿を見たことを書くことはできるが)。(後略)
-

パン・ヒョンソク(韓)
BANG Hyeon-seok平壌行の飛行機の中で受けた母国語試験と韓国文学の未来
パン・ヒョンソク (BANG Hyeon-seok)
1910年……日帝の侵略と植民地支配36年.
1945年……独立と分断と戦争、そして休戦65年.
2018年……( )
韓国語はこの空欄をどう満たすことになるだろうか。
2018年4月27日、板門店で出会った韓国語が世界に中継された。南北朝鮮の首脳が、通訳を使わずに会談できる唯一の相手に会った。韓国の他の作家らがこの瞬間をどう受け入れたのか知らないが、私は感激したものの複雑だった。母国語を扱う作家なのに、母国語を使う半分の人生は、私の文学の中に入ってきたことがなかった。私の文学の中になかっただけでなく、耐えるべき半分の人生を扱っている北朝鮮の文学についても、知っていることがあまりなかった。その一方で、私たちは母国語の半分だけをかろうじて背負える不具の作家であるという、事実に対する自覚さえなく、文学をして、生きてきた。
生中継を通じてやりとりする文在寅大統領と金正恩委員長の対話を見守りながら、私は2005年の平壌でのことを考えた。
最初で最後に開かれた、南北作家大会実務代表として、私は北京にある北朝鮮大使館で訪問証の発給を受け、Js152便の高麗航空に乗って平壌・順安空港に向かった。当時、民族文学作家会議の事務次長をやっていた後輩作家1人と一緒だった。機内で配る「朝鮮民主主義人民共和国入国申告証」を受け取って私はつらかった。鴨緑江上空を通過しているという案内放送が出るまで、私は申告証の「国籍」欄の前にもたついた。大韓民国、韓国、南韓、南朝鮮……私は結局、単に「南」とだけ書いた。
まもなく順安空港に到着するという案内放送が出るまで、私は申告証のもう1つの空欄を満たせずにいた。「民族」だった。韓国民族、朝鮮民族、韓民族、倍達民族〔諸歴史書に見られる朝鮮(民族)の古名〕……難しい問題だった。隣の席に座った女性に尋ねた。その女性は返事の代わりに自らの入国申告書を広げて見せた。私がなかなか思い出せずにいた単語、「朝鮮の人」と記されていた。私は正解を見て、明らかに彼女と同じ民族だったが、彼女のような答を書けなかった。結局、私は順安空港に着陸する直前に「私たち民族」と書いた。(後略)
-

チェ・ウニョン(韓)
CHOI Eun-young戦争のない未来
チェ・ウニョン (CHOI Eun-young)
高校生の時、雑誌『ハンギョレ21』でベトナム戦争に関する特集記事を読んだ。韓国がどんな国も侵略したことがないと学んできたので、その特集記事は私に衝撃と悲しみを与えた。戦争が民間人大量虐殺、強姦、拷問を含むという事実も、私はその記事を読んで知った。ベトナム戦争について知りながら、何気なく見たりした戦争関連のニュースに、それ以上無関心でいることはできなかった。
22歳の頃、旅行でベトナムの修道女に会ったことがある。私はその修道女に「韓国がベトナムで犯したこと、申し訳ありません」と謝った。「過ぎ去ったことです。大丈夫よ」。その人はそう言ったが、その瞬間、互いに分かち合った心を忘れることができない。24歳の時にはベトナムで2週間過ごすことがあった。そこでの仕事で会ったベトナムの友人に招待されて家に行った。その友人のお父さんが準備してくれた大きな食卓と、家族たちの暖かな歓待は、いまだに大切な記憶である。
「シンチャオ、シンチャオ」は私が出会った親しいベトナムの人々のことを思い出しながら書いた短篇小説である。この小説は1995年、ドイツのプラウエンという小さな都市が背景である。ここで韓国人の「私」の家族とベトナムのトゥイの家族が出会う。2つの家族は互いに好感を持ち深く頼り合う。韓国人少女の「私」は、ある夕食の時間に「韓国はどこの国も侵略したことがない」と誇らしげに話す。そのように学んできたから。この一言によって平凡だった夕食の席は、傷ついたホーおじさんの家族と、その傷を認めようとしない「私」の父親の葛藤へと拡がる。
「私」の友人トゥイはその場でこう言う。「韓国の軍人らが殺したんだ。彼らが母さんの家族をみな殺しにしたんだ。ばあちゃんも、赤ん坊だった叔母までも、そのままみな殺しにしたんだ。母さんの故郷には韓国軍憎悪碑があるんだから」。
申し訳ないと頭を下げる「私」の母とは違って、「私」の父はこう語る。
「私が何を言えばいいんだい? じゃあ、私たちが間違っていと言わなきゃいけないのか? なんでおまえが先にすまないって言うんだ? おまえは何だ?」。彼は韓国軍によって家族が抹殺されたウンウェンおばさんに言う。「もう終わったことじゃないですか? 申し訳なかったと拝まなきゃならないことだと思いますか?」。彼の兄はベトナム戦で戦死した。彼は傷ついた気持ちで、ホーおじさんの家族の話を聞かずに、心からの謝罪をしない。結局、2つの家族の距離は遠くなる。
-

レイ・ピンヤン(中)
LEI PING YANG未来について書く
レイ・ピンヤン (LEI PING YANG)
私の執筆の経験からして、「未来」という言葉は美的な特性を持つ一方で、疑わしいものでもある。美的特性の範疇において未来とはまだ明かされていないもののすべてで、想像のなかのあらゆるものと虚空のなかのあらゆるものとを意味しており、これは詩を書く過程のすべての精神的資産と、永遠に覚めない天国についての夢に近い。そして未来が依然として疑わしいのは、今日我々が虚弱なペンと思想欠乏が矛盾し合っている渦巻きの中に処し、現実に対する統制不能と未来についての無知によるメンタル崩壊と恐怖に直面しているにもかかわらず、むしろ我々のペンはいつも未来志向的であり、未来の人々のために書いているように包装されてきたという点であり、さらに未来はまるで創作のために悲しく死んでいったすべての物書きたちの天国のようにみなされてきたという点である。
1946年、ロシア系の天体物理学者ガモフ(George Gamow, 1904-1968)はアメリカの空軍機に乗っていろんな所を回りながら巡回講演をしていた。ある日、彼がニューヨークのあるカフェで静かに座っていたとき、実際に一瞬大脳の中で原子と亜原子が旋回し、分子と行星、銀河界と超銀河団が旋回しているのを目の当たりにした。そこで直ちに自分が見たものすべてをカフェの計算書の裏に数学公式の形式で素早く記録した。しかし後ほど、彼はその当時自分が一気で書きおろした粗雑な字を読み解けなくなり、あの瞬間神様が授けてくださったような秘密情報を失ってしまった。ドイツの芸術家クルガーとリヒターは再びこのことに触れて、ガモフが自分の過去の筆跡を識別できなかったから、「彼は以前のように正確にこの世界をみることができなくなった」と語った。
(後略) -

レイ・ピンヤン(中)
FU YUE HUI大風歌
レイ・ピンヤン (FU YUE HUI)
私の家の裏庭に竹がけっこうたくさんあったのだが、その竹林の隣に大きなセンダンの木が一本立っていた。センダンの太い幹はまっすぐに伸び、竹林を越えいつのまにか二階建ての高さにまで育ち、小枝を四方に伸ばした。ついには小さな道を渡り向かいの王さんの家の屋上にまで食い込む勢いだった。毎年春が来ればセンダンに花が咲くのだが、紫色の五つの花びらが枝いっぱいにつき、いきいきと軽く揺れ、ほとんど葉が見えないほどだった。
春の日に、竹林がひゅうひゅうと音をたてるほどの激しい風が吹くと、竹が前後に揺れ、しおれた落ち葉が空いっぱいに舞った。春が来たというよりは、むしろ冬に逆戻りしたようだった。よく見ると飄々と舞う乾いた竹の葉の間に、ごく小さな紫色の花が混じり、まるでパラシュートのようにくるくると空虚に落ち、小さな星のように裏庭を埋め尽くした。
裏庭には最初は土が敷かれていたが、後にセメントで固められた。何年か経ち、セメントに亀裂が入ると、その隙間にオヒシバとカナムグラが育ち始めた。雑草が育ちすぎて生い茂ると、私たちの足は裏庭から遠のいた。また月日が経ちセメントがなくなり、土の土地に原状回復したものの…何度こういったことを繰り返したか知れない。裏庭の垣根も同様で、最初は土レンガで作られた土塀に瓦をかぶせものだった。土塀が崩れると、空っぽのレンガを積んで低い垣根をを作ったのだが、いつかのまにかレンガの塀に亀裂が入り始め、その隙間から臭靈丹草が青々と育ち、今にも崩れそうになった。どれくらいの月日が経ったか分からないが、以降、新たな塀をこしらえ…庭にもたらされた変化は、まるで激しい風が新しい季節を呼ぶかのようであった。
-

中村文則(日)
NAKAMURA Fuminori (PHOTO©KENTA YOSHIZAWA)未来に
中村文則 (NAKAMURA Fuminori (PHOTO©KENTA YOSHIZAWA))
僕は小さい頃から、それほど明るい人間ではありませんでした。
自分も人間なのですが、人間が恐ろしく、毎日に生き難さを感じるような子供でした。人間とは何だろう。この世界は、なぜこんな風に存在しているのだろう。生きるのが辛かったので、そんなことばかり考えていました。そして高校生の時に限界に達して、学校に行けなくなりました。
日本の学校では、みな同じ制服を着ます。同じ格好をした人間が、同じ時間、同じ部屋に入り授業を受けるという、その当たり前のことが急に不気味に思えたのです。
集団生活ができないなら、先が思いやられる。自分はこれからどうやって生きればいいのだろう。十代の頃、そう真剣に悩みました。
そんな時に、救ってくれたのが文学でした。太宰治や、芥川龍之介といった作家達です。
当然のことではあるのですが、こんな風に悩んでいるのは自分だけじゃない、と思えたことが、とても救いだったのです。僕が文学にのめり込む、きっかけにもなりました。その後はドストエフスキー、カミュなど、読書の傾向が世界の作家達にも広がっていきました。(後略)
-

上田岳弘(日)
UEDA Takahiro (PHOTO©SHINCHOSHA)“未来”に引かれて
上田岳弘 (UEDA Takahiro (PHOTO©SHINCHOSHA))
かれこれ16年前のことになる。当時僕は早稲田大学に通う学生で、大半の文系学部の大学生のご多分に漏れず、最小の労力でいかに効率よく単位を取得するかを美徳とする一大学生だった。単位の取得が容易な科目を知るために学生有志が発行する雑誌まで販売されていた。そんな文化が今も残っているのかどうかはしらないけれど、多分残っているのだろう。良かれあしかれそう言ったものはなかなか変わらないものだ。
僕が隣国のことをはじめて身近に感じたのはそんな大学生の頃のことだ。所属していた国際法のゼミで、韓国に皆で訪問する企画が持ち上がったのだった。東京からなら、沖縄より近い位置にある、近くて遠い国。指導教授の肝煎りの企画で、韓国からの留学生による「韓国語特別講座」をする手筈まで教授が整えた。自由参加だったが、暇を持て余した大学生のこと、多くのゼミ生が参加した。たしか日韓共催のサッカーワールドカップが行われた年のことだ。にわかに両国の距離がぐっと近くなりつつあったものの、物理的な距離の割に、当時の日本はまだ今ほどは韓国になじみがなかった。
慣れない言葉を習得するためには、学ぶ者は言語習得をはじめた年齢に戻って、隣国からやって来た留学生が読みあげた例文を幼子のごとくリピートした----らしい、と伝聞口調になってしまうのは、僕はその韓国旅行に参加せず、したがって特別講座にも参加しなかったからだ。
参加したゼミ生から漏れ聞こえてきたのは、以下のようなことだった。
「韓国語の響きがとてもチャーミングである」
「それを読み上げる女性講師の声がまた可愛い」
「ファジャンシー、オディエヨ。これだけは覚えとけ」
ゼミ員たちの楽し気な口調に、早々と不参加を表明した僕は後悔した記憶がある。「韓国語特別講座」だけでもこっそり受けに行こうかと思った。(後略)
-

キム・グミ(韓)
KIM Keum heeだから相変らずわからない
キム・グミ (KIM Keum hee)
編集者として仕事をして20代の時期を過ごした私は、いったい、いい本はどう作るのか、私たちは出版労働者としてどのようなキャリアを積んで生きるべきか、私の手でベストセラーを誕生させることができるのか、という悩みを解決するために、ある団体でおこなう出版関係のセミナーを受けた。政府で費用を支援し、1週間に1度、1時間ぐらい早く会社を出なければならないので、会社側の配慮が不可欠の自己啓発の時間だった。講師は大部分、出版社の社長で、受講生は私のように出版社の社員だったが、私たちを共通に包んでいた、あの気だるい午後の、活気のない雰囲気を記憶する。たしかにすでによく売れる本を作っていたならば、あえてあのような場に行って再教育を受けるはずもないから、そこに熱い情熱と興奮があったとすれば、それも妙なことだったかもしれない。最初の決心と異なり、私もやはりその空間のおかしな無気力にそろそろ馴染みだしたころ、講師として登壇したある出版社の社長が、その後、私が一生忘れることのできない宣言を1つしたのである。それは、世の中にはおかしな読者が3000人いて、どんな本を作ろうと売れることになっているという、類まれな話だった。そのときすでに初版部数も消化できない一連の企画をやってきた私は、その話に半信半疑ながらも、耳がますます大きく開いていった。(後略)
-

シム・ボソン(韓)
SHIM Bo-Seon空の下、新しいものは多い
シム・ボソン (SHIM Bo-Seon)
読者は私をいつも驚かせる。私がある意図で書いた詩句を、さらにどんな意図で書いたのかも忘れてしまった詩句を、読者は驚くべき方式で解釈する。彼らは私が創作した狭い脈絡を巨視的に広げて歴史性と社会性を付与し、広い脈絡を微視的に狭めて生々しさと肉体性を付与する。
ときおり読者はささいな文章や単語にこだわる。彼らは数字に注目したりもする。なぜ14でも16でもなく15なのか? あるいは反対に、批評家が用心深く解釈する部分で、読者は果敢に飛躍する。家族史に関するメタファーが、読者には「パルチザンの話」になる。なぜ読者は、時にはささいに、時には果敢に、解釈を敢行するのだろうか?
読者は拘束を受けないからである。文学史や批評理論という学術的コミュニケーションの参照枠が彼らには必要ない。あるいは、そのような参照枠を使っても、それは解釈の主要指針でなく、選択可能な手段ないし資源に過ぎない。読者は概念を使う時、学問共同体を念頭に置かない。彼らは自らが発見した秘密の話を聞かせる人々を想像して興奮する。
したがって、読者にとって解釈と経験は分離していない。私は自分の作品の中で何の意味もない「宝くじ予想当選番号」を書いたことがある。だがある読者は、「実際に」その番号で宝くじを購入し、「実際に」5000ウォンに当選した。読者はその番号にある種の魔術的な意味を付与したのかもしれず、あるいは単なる興味でその番号で宝くじを購入したのかもしれない。ある書店が準備した「読者との出会い」で、その読者はその経験談を私に聞かせてくれた。私は、自分の詩にまったく深奥なところがなく、その一方できわめて独特な解釈作業を通じて、「現金化」される唯一無二の経験に接した。私はその読者に冗談で言った。「その5000ウォンを、私とあなたで分け合いましょうか? 私の分はありますか? あるとしたらどれくらいでしょうか?」。その場にいた人々はみな大声で笑った。(後略) -

スィ・クン (中)
XU KUN読者を探します
スィ・クン (XU KUN)
三十余年前創作について学びはじめた当初、私は私の読者が誰なのか知らなかった。そして誰が私の文章を読むのかといったことも全く関知しなかった。あの時はひたすらに荒っぽい気勢で真摯に文章を書きつづけながら一途に前に進んだ。空威張りをして、周りに見向きもしなかった。「青春」と呼ばれる強い東風の力で春の水が増し、春の潮が高くなるように、汪洋たる内面に体をあずけ、ペン先で思う存分踊りながら北京の乾燥した砂地を力いっぱい走りぬいた。
そうしてから、私はハチの群れのように読者が押し寄せてくるのを目の当たりにした。様々な読者がいた。男も、女も、年寄りも、少年もいた。いろんな観客が幾多の容姿をもっていた。 砂地で涼しい風に当たりながら見物する人々もいたり、伝統を守る厳正な批評家もいたりした。ある人は見上げ、ある人は見降ろした。賛美し称揚する人もいれば、ケチをつけたり上げ足をとる人もいた。耳に痛い忠告にしろ、あるいは過分な賞賛にしろ、私は珍奇な宝物を手にいれたかのように望外の喜びで何でも受け入れた。
なぜなら、何はともあれ、文章で切り拓いた心の道は、一瞬にして心を通い合わせ、向こう側まで到達できることを知っているからだ。その道はこの世界に到着し、人々の心に到着した。「読者」が存在したので、私はこの広大な世界と精神的に結ばれることができたのである。読者がいてくれたので、私は2,500万の人口が住む北京という大都市にて独りぼっちにならずに済んだ。読者がいるところに作者がいる。そして作者がいるところに読者がいる。この両者は切っても切れない緊密な対象的関係をなしている。作家は現実と歴史にたいして読者が「吐露」しようとする欲求を満たしてくれる。そして読者は作家たちが世の中においての存在感を持たしてくれる。(後略)
-

ワン・ウェイレン (中)
WANG WEI LIAN書くことは読むことを呼び、創造している
ワン・ウェイレン (WANG WEI LIAN)
自分の創作についてあらためて振り返りながら、あることに気付いて驚いた。書くことを始めて以来、ほとんど読者を念頭に置いてこなかったのだ。誰が自分の作品を読むのか、全く考えてこなかった。それは傲慢ではなくむしろその正反対の謙遜であって、それから自分が長く読者であってきたからだといえる。自分はきっと作家にはなりえないだろう。しかし自分が本を読まずに完全に現実にだけ埋没している姿を想像することはできなかった。読書は現実とはまた別の空間であり、書くことと読むことは同じ場所に進み入ることだ。詩人ミウォシュ(チェスワフ・ミウォシュ、1911-2004 ポーランドの詩人・訳注)が残した「第二の空間」という文学の定義を借りたい。この空間は形式的に私たちの現実空間の上に君臨しているのではなく、現実空間と複雑に混じり合い、対話関係を維持している。
読者として、私はいろんな国の文学作品を多く読んだ。韓国と日本の文学作品を読むと、他の国の作品とは違う読後感があった。不思議な親しみがわくのだ。家族に対する格別な配慮や深みある感情表現は中国人の心に響いた。私たちは、自然にそれを儒教文化によるものとすることができる。なぜ儒教文化はあり、受け入れられたのか。間違いなくこの生命概念と生活規範について、深い部分で似通っているからだと思う。こうした類似性を手がかりに、韓国と日本の作品が私にもたらしてくれた親しみを解きほぐしてみたい。韓国と日本の文学の中に探し求めたいのは、その近い土地から文化を呼び起こす力だ。(後略)
-

島本理生(日)
SHIMAMOTO Rio (PHOTO©HAYATA DAISUKE)読者
島本理生 (SHIMAMOTO Rio (PHOTO©HAYATA DAISUKE))
文芸誌の新人賞に小説を応募して、作家としてデビューしたのが2001年の十七歳の春だった。
年齢が若かったこともあり、身近な題材であった恋愛をこれまで主に書いてきた。
高校教師と元教え子の恋愛を書いた『ナラタージュ』が代表作として扱われ、行定勲監督によって昨年に映画化されたこともあって、作家としての私を説明する際には、恋愛小説家、という表現を用いられることが多い。
一方で個人的な関心は、恋愛というよりは、「恋愛と似て非なるもの」にある。
読者層も、自分と同年代の三十代から、大学生、高校生といった比較的若い女性が大半を占めるため、そういった読者にむけて、表面化しない性暴力や虐待のトラウマについて書きたい、という思いが根底にある。
なぜなら思春期の少女たちにとって、大人の巧妙な支配欲や性欲は、一見、恋愛と酷似しているからだ。
私が青春時代を過ごしたのは90年代後半から2000年代前半の東京で、日本ではバブル末期にあたる。その余韻が完全に消失するまでの数年間であった。
ただ、90年代後半はバブルが弾けたとはいえ、東京にはまだその残り香が十分に漂っていた。
なんでもお金で手に入れようとすることへの無頓着さと、そんな時代の終わりの不安とが混在していたように感じる。世紀末という言葉も、そんな空気をより濃くしていた。
女子高校生がお金をもらって大人と肉体関係を持つ「援助交際」という言葉が流行していたのは、私自身が高校生のときだ。
-

柴崎友香(日)
SHIBASAKI Tomoka (PHOTO©KAWAI HONAMI)距離と読者
柴崎友香 (SHIBASAKI Tomoka (PHOTO©KAWAI HONAMI))
わたしが初めて、外国の作家たちと交流する今日のような場に参加したのは、2010年12月、今回フォーラムが開催されるのと同じ、ソウルでのことだった。日本と韓国と中国の文芸誌がそれぞれの作家の短編を掲載するという企画の一環で、ソウルを訪れたのも、そのときが初めて。三つの国の作家が登壇した場で日本語で短いスピーチをし、それがまず韓国語に通訳された。しかし、そこには日本語と中国語の通訳者はいなかったので、韓国語から中国語へと通訳されることになった。一段階目までは、来場者の反応などからなんとなくどの部分を話しているかわかったのだが、二段階目ではまったくつかむことができなかった。
それまでわたしは、翻訳されるということ、外国の文学を読むということは、遠くにあるものがだんだん自分に近づいてくるものだと思っていた。しかしそのとき、翻訳とは自分から遠ざかっていくことでもあると知った。そして今は、翻訳だけでなく、小説を書くことそのものが、書いた時点から自分から遠ざかって行くことなのかもしれないと思う。遠ざかっていったその先に、読者がいるのだと。
2010年のソウル以来、わたしは日本でも外国でも、作家や読者と交流する機会が増えた。ニューヨーク、カリフォルニア、台北、ロンドン、マンチェスター、北京、上海。2016年には、アイオワ大学の国際創作プログラムにも参加した。韓国や中国からも参加した作家が複数いる歴史あるプログラム。詩人や脚本家なども含めて「writer」たちが三か月近く同じ場所で生活し、それぞれの言葉で書かれた作品を英語を介して、互いに読み、朗読を聞き合うという貴重な機会だった。(後略)




